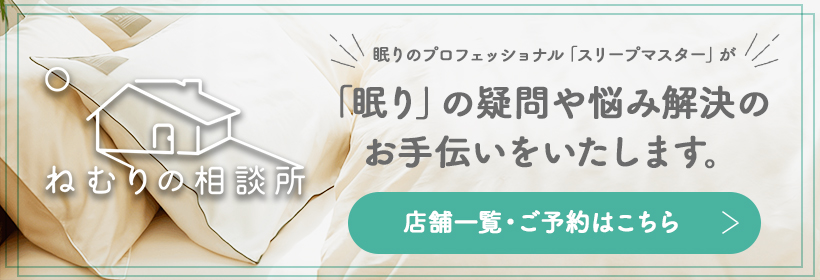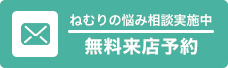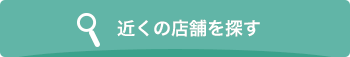「最近眠りの質が良くない気がする」
「季節の変わり目に寝不足を感じる…」
「冷え性でなかなか寝付けない」
このように感じたことがありませんか?
実は、睡眠と体温には深い関係があり、睡眠の質に大きく影響しています。
空気が冷える冬場は、体温調節がうまくできなくなります。
今回は、睡眠と体温の関係から、快眠のためのポイントをご紹介いたします!
ぜひ最後までご覧ください。
目次
睡眠と体温の関係性について

人は、寝ているときの体温が低くないと、目が覚めてしまいます。
この寝ているときの体温とは、中心部の温度のことを指しており、深部体温と呼ばれています。
具体的には脳や内臓の温度で、眠る少し前から徐々に深部の体温が下がり、快適な睡眠に導きます。
反対に、深部体温が高いままだったり布団内の温度が高すぎると、深部体温も上昇してしまい良い眠りの妨げになるのです。
人は無意識のうちに、深部体温をコントロールして一日を過ごしています。
睡眠時の身体機能から、睡眠と体温の関係性について見ていきましょう。
睡眠は2つの身体機能で調節されている
睡眠は、主に2つの身体機能によって調節されています。
それが「体内時計」と「熱産生・熱放散」と呼ばれる機能です。
体内時計
「体内時計」は、1日のリズムを刻む、言わば脳内にある時計のことです。
毎日同じ時間帯に眠くなるなど、その存在を自覚している方も多いのではないでしょうか。
「体内時計」からの指令によって、夜になると深部体温が下がるようになっています。
これは、夜の間は日中のように活動をする必要がないからです。
熱産生・熱放散
一方、「熱産生・熱放散」は聞き慣れない言葉かもしれませんが、誰もが無意識のうちに使っている機能です。
これは文字通り、熱を体内で作ったり体外へ逃がしたりすることで、体温を調節する働きのことです。
例えば、寒い時に体がブルブルと震えるのは、熱を産生して体を温めるためです。
反対に暑い時に汗をかくのは、熱を放散して体を冷やすためです。
睡眠では眠りにつく際に「熱放散」が行われます。
これは手足から熱を逃がすことで、相対的に深部体温を下げることができる機能です。
眠くなっている赤ちゃんの手足が温かいのはこのためです。
このように、「体内時計」と「熱産生・熱放散」の2つの機能によって、体温に変化が引き起こされ、睡眠状態に入るよう調節されているのです。
眠りが深ければ深いほど、深部体温は低くなると言われています。
これは眠ることで代謝が下がり、体内で生み出される熱の量が少なくなるためです。
つまり、睡眠もまた体温調節に関わっているということです。
睡眠と体温は、互いに影響を及ぼし合っているのです。
体温が高いと不眠になる?

これまでの話をふまえると、体温が高い方が不眠になりやすいと思われるかもしれません。
しかし、実はそのように単純な話ではありません。
と言うのも、体温が高い時期に分泌されるホルモンに、睡眠を深くする作用があるためです。
女性の基礎体温は一定では無く、低温期と高温期が交互に存在していますが、高温期に分泌されるホルモンの働きによって、基礎体温が変化しても睡眠は一定に保たれているのです。
一方で、更年期初期に見られる不眠には、別で注意が必要です。
更年期では、体温変化に先立ってホルモンの分泌が減少してしまうので体温が安定するまでの間、不眠が出現してくるわけです。
寝不足と体温の関係

快適な睡眠をとるには、体温をしっかり下げることが関係しています。
深部体温を充分に下げることができれば、自然な入眠につなげやすくなります。
深部体温を十分に下げる
深部体温が下がっていないと、手足から上手に熱を逃がすことができません。
冷え性の方に寝不足の悩みが多く見られるのは、このためであると考えられています。
特に体温調節の難しい冬は、寝つきが悪くなってしまう傾向にあります。
逆を言えば、この体温調節さえ上手くできれば、快眠につながるということです。
睡眠中の深部体温を上げない方法

寝る前に深部体温を下げる準備をしたら、次は寝ている間に深部体温を上げないように工夫しましょう。
睡眠中に深部体温が上がりにくくするのは、寝室や寝具などの、環境を整えることが有効です。
室内温度を適正にする
睡眠時に深部体温を上がりにくくするには、季節に応じた室内温度にすることがポイントです。
寒い冬は、つい寝室を暖めたくなってしまいますよね。
しかし、強すぎる暖房で室温を上げすぎると、睡眠の妨げになります。
室内温度は冬10℃以下、夏は28℃以下にするのが目安です。
エアコンについているタイマーも上手く活用して調節しましょう。
頭を冷やす
頭を冷やすことも、室温を下げたのと同じ効果が得られると言われています。
「頭寒足熱」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
寝ている間は、正にこの状態が理想なのです。
頭に冷たいものをあてて直接冷やすと効果的です。
また、寝る前につい見てしまいがちなのがスマホやテレビの画面です。
画面を見ると、脳の温度は上がってしまいます。
この習慣をやめることも、頭を冷やすことにつながります。
体を温める寝具を適切に使う
寒い時期は、電気毛布や電位・温熱敷き布団を使っている方もいるでしょう。
しかし、これらの電源をつけたまま寝てしまうと途中で布団の中の温度が上昇しすぎてしまいます。
布団の中の温度が上昇すると、必然的に体温も上がってしまうので暑くて夜中に目が覚めてしまう原因となります。
途中でタイマーをかけて電源を切るなど温度調整をし、寝具を適切に使うようにしましょう。
寝不足を解消して適切な体温を保つには

睡眠中の体温を理想的な状態に保つには、深部体温を上げてから下げることが効果的です。
一度深部体温を上げることで、眠りにつく頃に深部体温が下がりやすくなるためです。
日常の生活習慣から睡眠の質を上げることができます。
就寝前の行動で取り入れられるものをチェックしてみましょう。
運動をする
夕方から夜にかけて、ランニングなどの有酸素運動を20~60分すると良いと言われています。
特に16時ごろに運動をすると一時的に体温が上昇し、就寝する時間に向けて少しずつ体温を下げることができるので、夕方の有酸素運動がおすすめです。
体温の落差を意識して、運動を取り入れてみましょう。
ただし、就寝直前に激しい運動をしてしまうと、体が興奮してしまい不眠につながるので注意が必要です。
夜は、遅くとも寝る3時間前頃までには運動を済ませることをおすすめします。
入浴をする
就寝前の入浴は効果的で、就寝の1時間前までに、ぬるめのお湯に入るよう心がけましょう。
リラックスできるお湯の温度は約40℃、時間は15~20分が理想と言われています。
入浴をすることで、深部体温が上がり、就寝する頃に眠りやすい体温に下がります。
ただし、熱すぎるお湯では深部体温が必要以上に上がってしまうので注意が必要です。
食事のタイミング
食事をとると、体や脳は食べたものを消化するために活性化します。
そのため、体温が上がることになるので、食事は睡眠の2~3時間前までに済ませましょう。
さらに睡眠の質を向上させたいという方は、バランスのとれた食事を取ると良いです。
一方で飲酒は睡眠の質を下げてしまうのでほどほどにしておきましょう。
適正な深部体温へ調整を行いより良い睡眠へ
睡眠と体温は互いに切り離せない関係にあることがわかりました。
この仕組みを頭に入れておき、体温を上手くコントロールすると快適な眠りに近づくでしょう。