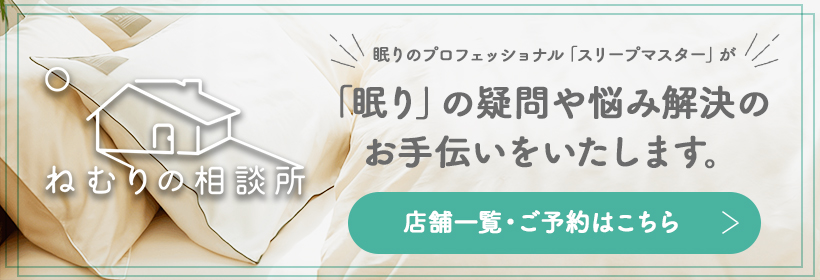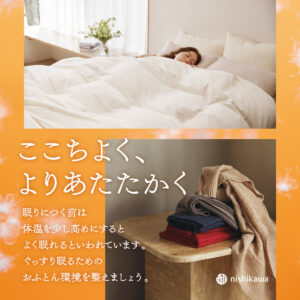年を重ねるに連れて眠りにくくなってくるのは、年齢ごとに適性な睡眠時間が異なるからです。自分の年齢にあわせた睡眠時間を取ることで、起床しやすくなり日中の活動量も増やせる可能性があります。
しかし、年齢ごとの適性な睡眠時間がわからず悩む人もいるのではないでしょうか。
この記事では、年齢ごとの適正な睡眠時間や確保するコツを解説します。自分の年齢に必要な睡眠時間を理解して、確保できる起床・就寝時間を決めましょう。
目次
年齢によって適正な睡眠時間は変わる

毎日の睡眠で取るべき睡眠時間は、年齢とともに変わっていきます。とくに、幼少期は成長に必要なホルモンを分泌させるために、睡眠は欠かせないものです。(※1)
年を重ねるにつれて成長ホルモンは分泌量が少なくなり、青年期は10時間必要だった睡眠時間も、高齢者になれば少なくなります。このことから、高齢者になってからも幼少期と同じ睡眠時間は不要になり、年齢にあわせた睡眠時間を取ることが必要になります。
【年齢別】適正睡眠時間一覧

適正な睡眠時間は年齢によって異なるため、自分に必要な時間を理解しましょう。
ここでは、年齢別の適正睡眠時間を解説します。
- • 青年(14~17歳):8〜10時間
- • 若年成人(18~25歳):7〜9時間
- • 成人(26~64歳):7〜9時間
- • 高齢者(65歳以上):7〜8時間
なお、今回の睡眠時間は【米国国立睡眠財団による年代別推奨睡眠時間】を参考に解説します。
青年(14~17歳):8〜10時間
米国国立睡眠財団による年代別推奨睡眠時間では、14〜17歳の青年に必要な睡眠時間を8〜10時間としています。この睡眠時間は、3~5歳が10~13時間・6~13歳が9〜11時間とされていることから、成長につれて必要な睡眠時間が減っているとわかります。
若年成人(18~25歳):7〜9時間
18~25歳に必要な睡眠時間は、米国国立睡眠財団による年代別推奨睡眠時間では7〜9時間とされています。この年齢になると社会人として働き始める人もおり、7時間の睡眠を確保することが難しいと感じる人もいるかもしれません。
ほかにも、大学生活で講義やアルバイトの忙しさから、睡眠時間の確保が難しい人もいるでしょう。
成人(26~64歳):7〜9時間
26〜64歳では、7〜9時間と18〜25歳と同じ睡眠時間が必要です。この年代は多くの人が働いており、プライベートの時間との兼ね合いで睡眠時間が短くなる人も少なくありません。
しかし、忙しいなかでも睡眠時間を確保することで、休日も起きやすくなり、プライベートの時間を確保しやすくなります。
高齢者(65歳以上):7〜8時間
65歳以上の高齢者では、7〜8時間の睡眠が必要とされています。厚生労働省が発表する健康づくりのための睡眠ガイド2023では、長い就寝時間が健康リスクにつながる可能性があるため、8時間以上の睡眠は推奨されていません。
また、日中の昼寝も夜の睡眠に影響する可能性があるため、おすすめできない行動です。
適正睡眠時間を確保する方法7選

睡眠時間を確保するためには、スマホを見る時間を減らし、生活リズムを整えるための行動が大切です。自分の生活を振り返ってみて、直せる部分がないかを考えましょう。
ここからは、適正睡眠時間を確保する方法を7つ解説します。
- • スマホをだらだら眺める時間をなくす
- • 起床・就寝時間を固定する
- • ゆっくり入浴する時間を作る
- • 寝る数時間前に食事を済ませる
- • 寝る前のカフェインやアルコールを避ける
- • 自分にあった寝具を使用する
- • 自分の睡眠状況を把握する
スマホをだらだら眺める時間をなくす
年齢にあわせた適正睡眠時間を確保するためにも、スマホをだらだらと眺めるだけの時間を減らしましょう。
近年では動画配信アプリの普及により、眺めるだけで楽しめるコンテンツが数多く存在します。なんとなく眺めているだけでも、気がつけば時間が経ってしまい、睡眠時間を減らす原因になりかねません。
スマホを眺める場合は時間を決めておき、その範囲のなかで使用しましょう。
起床・就寝時間を固定する
年齢にあわせた適正睡眠時間を理解できたら、自分の起床時間から逆算して、何時に就寝する必要があるのかを考えましょう。たとえば、25歳の人が朝7時に起床するのであれば、遅くとも0時には就寝しなければなりません。
起床・就寝時間を固定することで生活リズムも整い、寝つきや起床のしやすさにも変化がでます。まずは就寝時間を固定してみて、日中の眠気をもとに増減を検討しましょう。
ゆっくり入浴する時間を作る
適正な睡眠時間を確保するためには、就寝時間に眠気を起こさなければなりません。そのためには、湯船にゆっくり入浴する時間を作ることが大切です。
体が眠気を生じさせるのは、体温が下がるタイミングです。就寝の1時間半ほど前に入浴しておくことで、就寝時間に体温が下がり、眠気を引き起こしやすくなります。なお、入浴するときは40度前後のお湯に10〜15分ほど浸かると効果的です。
寝る数時間前に食事を済ませる
就寝時間に眠気を起こすためには、寝る数時間前に夕食を済ませておきましょう。
就寝ぎりぎりに食事を取ると、寝ている間も胃腸が消化活動を続けてしまい、負担がかかります。また、消化活動を続けている以上体が休まらないため、起床時の疲れにつながる可能性もあるでしょう。
寝る数時間前に食事を済ませておくことで、就寝時には消化が終わっており、すっきり眠れるようになります。
寝る前のカフェインやアルコールを避ける
寝る前にカフェインやアルコールを摂取していると、睡眠の質を下げてしまい適正な睡眠時間を取りにくくなります。
カフェインには覚醒作用があり、摂取すると眠りにくくなる可能性があります。アルコールも、入眠しやすくなる効果があっても、睡眠の維持が難しくなり、中途覚醒を引き起こす可能性があるのです。
寝る前は白湯やカフェインの入っていないハーブティーなどを摂取することで、眠りやすい状態になります。
自分にあった寝具を使用する
就寝時に使用するマットレスや枕などの寝具も、適正な睡眠時間を確保するために欠かせません。
たとえば、柔らかすぎる枕を使用している場合、頭を乗せたときに枕が沈み込んでしまい、寝返りがうちにくくなります。同じように、薄すぎる布団では床の硬さが気になってしまい、眠りにくくなります。
このように、自分にあった寝具を活用することで快適な睡眠がしやすくなるのです。
なお、市販品で自分にあった枕が見つからない場合は、オーダーメイドで作成する方法もあります。下記のページではオーダーメイド枕について解説しているため、ぜひ参考にしてください。

自分の睡眠状況を把握する
適正な睡眠時間を取っていても、睡眠の質が悪ければ日中の眠気につながります。起床時にすっきり起きられない、途中で起きてしまうなどに悩む人は、睡眠の記録をつけられるアプリを活用して、自分の睡眠状況を把握しましょう。
睡眠状況を把握することで、きちんと睡眠がとれているのかが理解でき、直すべき部分も明確になります。アプリによっては睡眠に対するアドバイスも得られるため、睡眠状況の改善に役立つでしょう。
睡眠状況の把握なら西川の睡眠アプリgoomoがおすすめ

睡眠状況の把握なら、西川の睡眠アプリgoomoがおすすめです。goomoでは何も身に付けずに使用者の睡眠状況を正確に把握し、睡眠の必要なアドバイスが可能です。
希望する起床時間にあわせて起きやすいタイミングでアラームを鳴らしてくれるため、寝起きが悪い人にも役立ちます。アラームの音は任意のタレントの声に変えられ、毎朝気持ちよく起床できるでしょう。
睡眠を記録するアプリに悩んだときは、ぜひgoomoから試してみてください。

年齢ごとの適正睡眠時間を理解して日々の生活に取り入れよう

適正な睡眠時間は年齢によって異なるため、自分にあわせた時間を確保することが大切です。適正な睡眠時間の確保が難しいときは、日々の生活を見直し、生活リズムを整えましょう。
また、自分の睡眠状況を理解することで、取るべき対策がわかる可能性もあります。西川のgoomoを活用して、快適な睡眠を手に入れましょう。
【参考】
※1 睡眠の質と深い関係にある成長ホルモンの知識